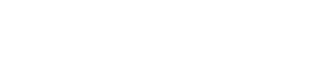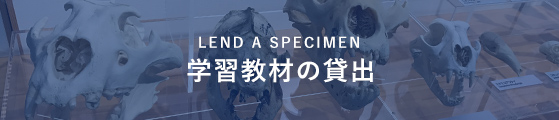BLOGいのちの博物館だより

《*本記事内には、標本作製途中の写真を掲載しています。苦手な方はご注意くださいますようお願い申し上げます。》
当館名誉学芸員の高槻成紀先生制作のアオゲラ骨格標本が収蔵されました。
エントランスに展示していますので、ぜひご覧ください。
経緯や作製過程については、高槻先生のブログよりそのまま抜粋してご紹介いたします。
【高槻先生のブログより】
アオゲラの骨格標本
長野県北部の信濃町にあるアファンの森ではときどき鳥がガラス窓にぶつかって死ぬことがあるそうです。
その中にアオゲラがあったので標本を作りました。
(写真1:アオゲラの死体)
羽毛を除き、内臓を摘出し、皮膚、筋肉を外した後、ポリデントにつけ、数日水を取り換えると骨格標本のもとができます。
それを針金の軸で支えて組み立てます。
(写真2:仮に組み立てたアオゲラの骨格)
それから尾羽をつけて、円柱に取り付けました。
アオゲラは樹上をす早く歩いて移動しますが、その時に体が安定するように両足と尾翼の3点で安定支持します。
そのためアオゲラの尾羽のうち中央の2本が太くがっしりしています。
(写真3:完成したアオゲラの標本)
この標本で注目したのはアオゲラの舌です。
キツツキ類は木の幹を突いて穴を開け、中の昆虫を食べることが知られています。
そのために長い舌を持っていますが、その舌は口から喉のほうを通りますが、そこで二股に分かれます。
そして後頭部を越して頭頂部を経て嘴の付け根に達します。
驚くべき長さです。
(イラスト:アオゲラの舌)
このことは知っていたのですが、実際に見ると驚かずにはいられません。
頭骨の皮膚を剥がすと確かに頭に枝分かれした舌が見えました。
(写真4:頭頂部から見た舌)
それを慎重に取り出しました。
(写真5:舌と頭骨)
もちろん舌そのものは筋肉です。
その中に舌骨が入っていますが、骨といっても柔らかい膜状のものです。
舌の筋肉を収縮させると、この舌骨が一瞬で前に押し出されて舌がビュンと飛び出す仕掛けです。
舌には粘液がついていて昆虫類をくっつけるようになっています。
舌の筋肉を丁寧に除去して舌骨を取り出しました。これを再び頭骨に戻してボンドで接着しました。
(写真6:舌骨をつけた頭骨)
*高槻先生のブログURLはこちらです。
アオゲラ
https://blog.goo.ne.jp/takahome12/e/a97c915a7f6970962c75c5e13431cac5
アオゲラ骨格標本
https://blog.goo.ne.jp/takahome12/e/adfbe8e425973cacf1ffcc3defad8d05
- いのちの博物館についてABOUT
- 施設案内・開館情報FACILITY
- 展示情報 EXHIBITION
- いのちの博物館だより BLOG
- 学習教材の貸出 LEND A SPECIMEN
- アクセスACCESS
麻布大学いのちの博物館 公式twitter