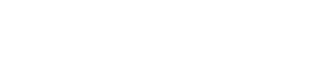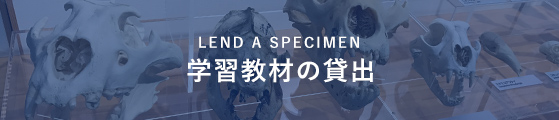BLOGいのちの博物館だより

※この記事は、名誉学芸員高槻先生にご寄稿いただきました。
開館10周年を記念して一部展示の入れ替えをしました。ひとつは「動物の食べ物」でこれまで2ケースを使っていましたが、ひとつにまとめました。左側のパネルに自然界での食物の質と量の関係を説明しました。代表的な肉食獣であるライオンやトラを左側に、草食獣のウマとガゼルを右におき、その間に雑食性のサル類をおきました。植物食の中には齧歯類のような果実食もいるので、リスとリスが割ったクルミも展示しました。肉食獣とサルの間に、頭骨では肉食獣の特徴を持ちながら果実を中心に雑食的なタヌキが食べた果実に含まれていた種子を展示しました。クマも同様に果実食に偏った雑食性です。(写真①)
これとは別に記念展示を2つ用意しました。これらは基本的にかつて展示したものです。
ひとつは「ロードキル」で、麻布大学周辺の交通事故にあったタヌキなどの頭骨をたくさん配列して展示しました。交通事故というと、「動物が死んだ」というイメージがありますが、実体は「動物が人に殺された」ので、キル(殺し)という言葉がふさわしいです。展示標本の中には頭骨が破損したものもあります。このような標本は、通常は博物館で収蔵しませんが、この標本群は交通事故の実態を記録するものなので、あえて破損標本も収蔵しています。また同じ動物の標本を60体もの多数展示することもあまりありませんが、この展示のメッセージは「たくさんの犠牲者がいること」にあるので、あえて多数を並べました。これにより、私たちが享受しているモータリゼーションの影に、こんなにも多数の犠牲者がいることをいることに想いを馳せてもらいたいと思います。(写真②)
もう1つの記念展示は「プラスチネーション」です。これは本学の二宮名誉教授が開発されたもので、毛細血管の微細構造の立体的把握に大きく貢献しました。学術的価値も高いもので、本学が誇るものですが、博物館の展示という意味でいえば、色彩的にも、形状も非常に魅力的で、本館の展示物が骨が多く、白が基調になっているので、このコーナーは異彩を放っています。展示内容はかつての企画展示と同様ですが、今回は多めの標本を展示しました。(写真③)
これに伴い、展示室の仕切りのようになっている両面ケースに哺乳類の頭骨を配置しました。これにより、肉食獣、草食獣の頭骨、歯の形、歯列などが比較しやすくなりました。また、肉食獣の代表としてイヌの胃の標本と、草食獣のうち反芻獣の代表としてヤギの胃の標本と、それぞれに対応するオオカミとヤギの頭骨を示しました。(写真④)
(写真①)

(写真②)

(写真③)

(写真④)

- いのちの博物館についてABOUT
- 施設案内・開館情報FACILITY
- 展示情報 EXHIBITION
- いのちの博物館だより BLOG
- 学習教材の貸出 LEND A SPECIMEN
- アクセスACCESS
麻布大学いのちの博物館 公式twitter